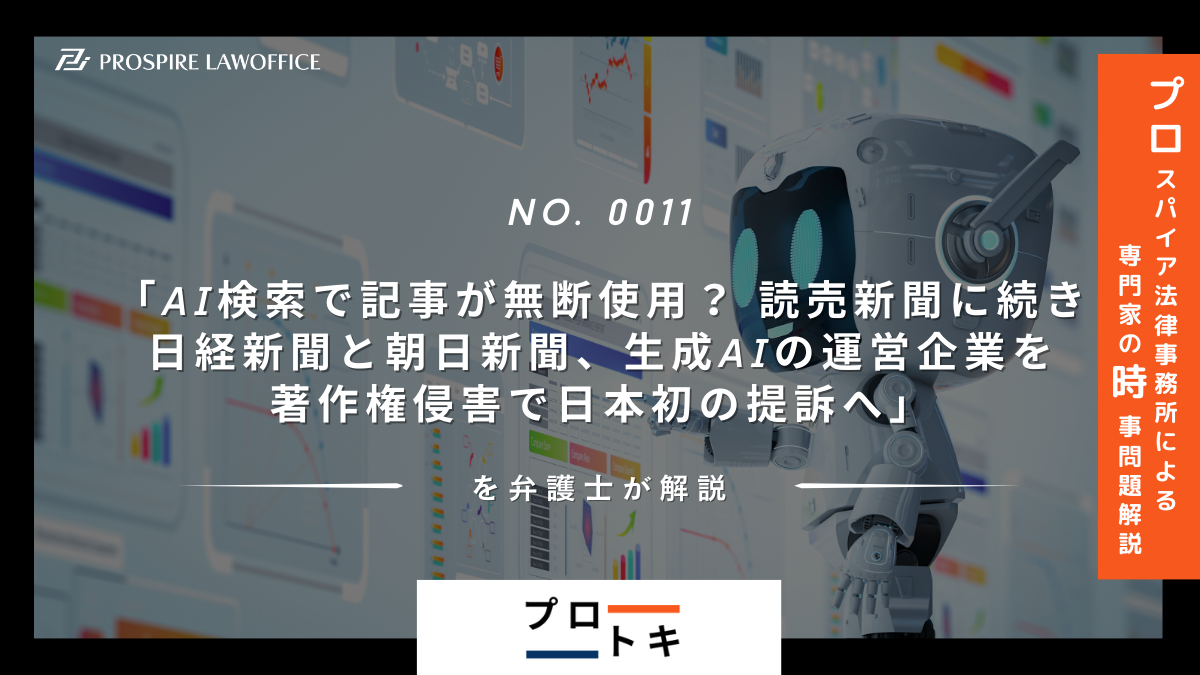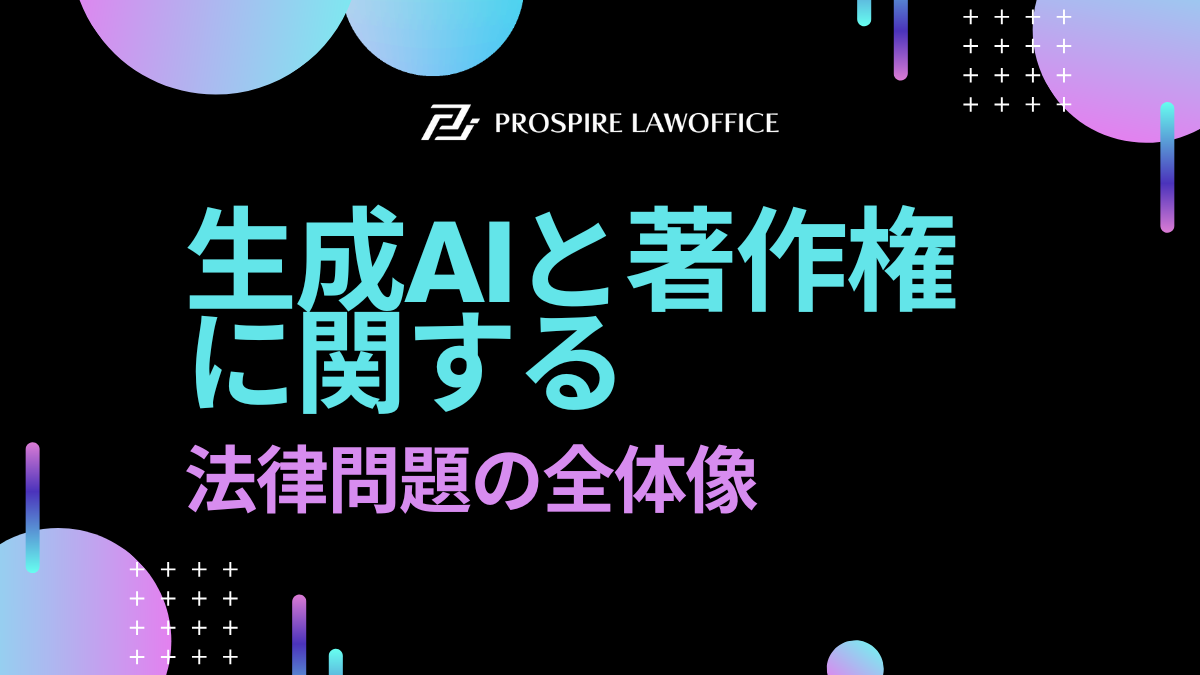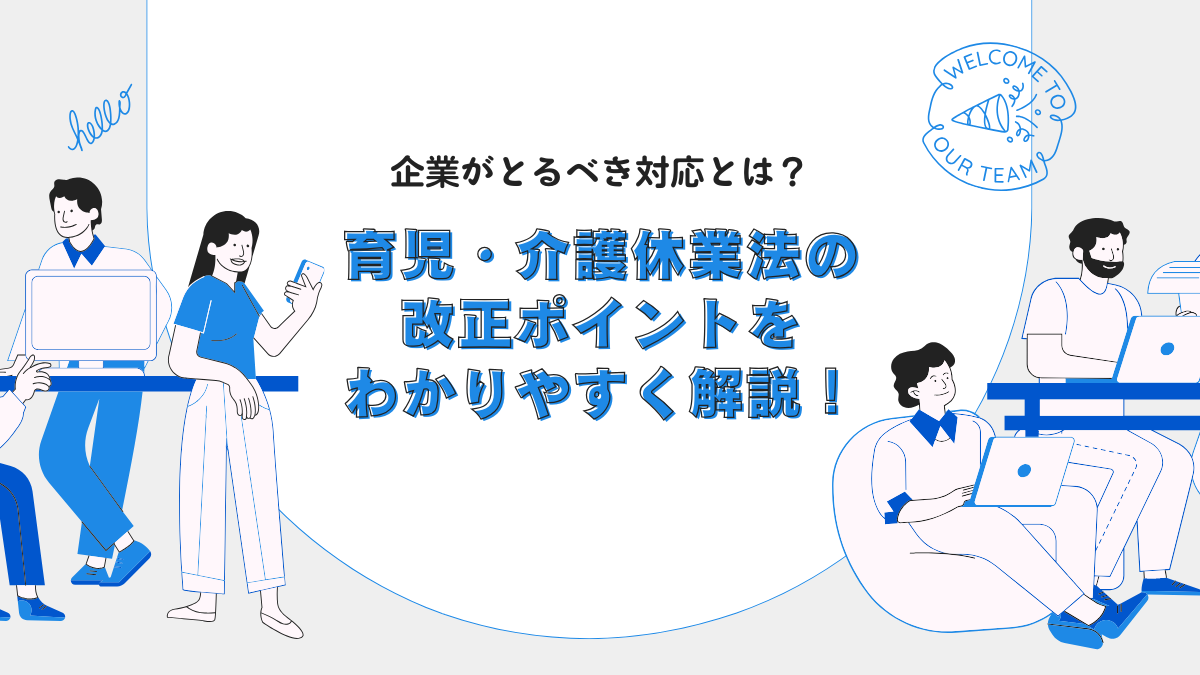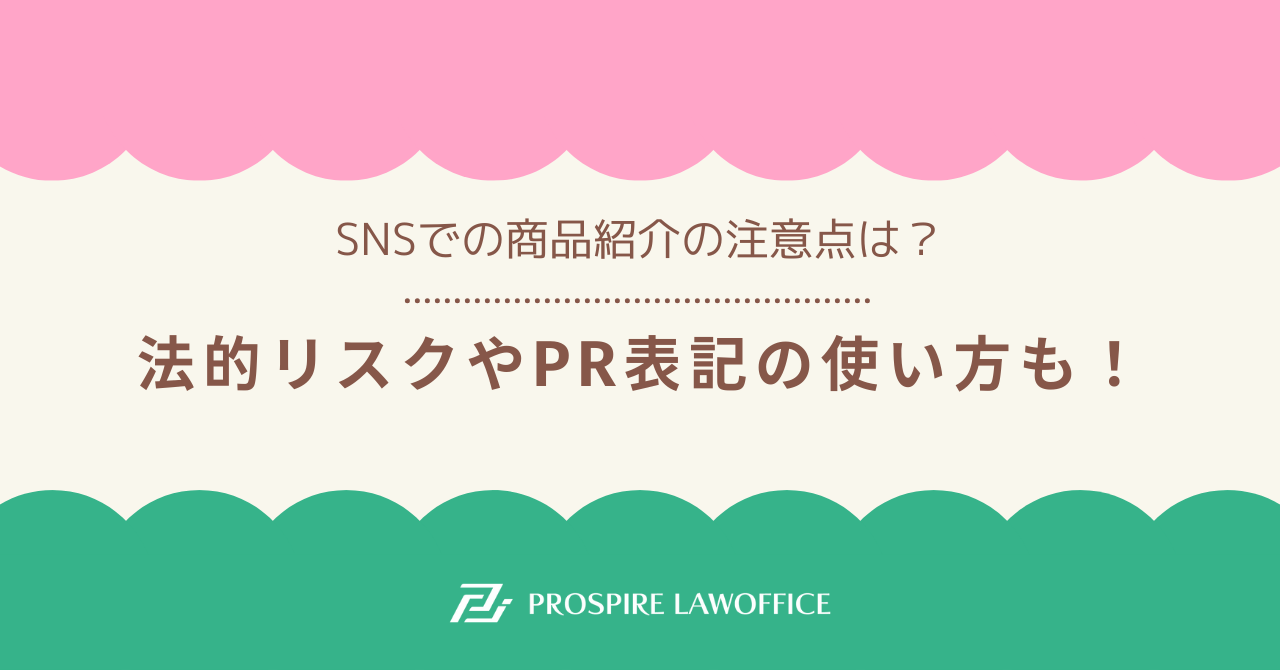連載シリーズ「プロトキ」では、プロスパイア法律事務所の弁護士等の専門家が、ニュースや時事問題について、法律の観点から解説をしていきます。
※本記事は、令和7年8月27日時点の情報に基づいて執筆されています。
今回は、「AI検索で記事が無断使用? 読売新聞に続き日経新聞と朝日新聞、生成AIの運営企業を著作権侵害で日本初の提訴へ」というニュースについて、生成AIによる検索は複製権・公衆送信権の侵害にあたるのか、ゼロクリックサーチによる営業妨害や海外メディアの動向など弁護士の目線から解説していきます。
ニュース概要
読売新聞グループ本社は8月7日、生成AI(人工知能)を用いた検索サービスを提供する米新興パープレキシティを東京地裁に提訴したと発表しました。
続いて、8月26日、日本経済新聞社と朝日新聞社も著作権侵害行為の差し止めと各22億円の損害賠償を求め同社に対し提訴したと発表しました。
参考:読売新聞オンライン|読売新聞社、「記事無断利用」生成AI企業を提訴…日本の大手報道機関で初
参考:日本経済新聞HP|日経・朝日、米AI検索パープレキシティを提訴 著作権侵害で – 日本経済新聞
AI検索による記事の無断使用が著作権を侵害しているとして、読売新聞者は、約21億6800万円の損害賠償と侵害行為の差止め、日本経済新聞社と朝日新聞社は、各22億円の損害賠償と侵害行為の差止めなどを求めています。AI検索を巡り日本のメディアが訴訟を起こすのは初とみられています。
こちらの記事では、生成AIによる記事の「複製権」侵害、要約コンテンツの「公衆送信権」問題、「ゼロクリックサーチ」による営業妨害などを詳しく解説します。
AI検索「パープレキシティ」とは?

米新興企業パープレキシティ(Perplexity AI)は、生成AI(人工知能)を用いた検索サービスを提供しています。このAI検索は、インターネット上で公開されているコンテンツを取得し、それを要約して文章として利用者に提供する点が特徴です。
パープレキシティは、米オープンAIの技術者が2022年に設立しました。設立以来、その革新的なAI検索技術は注目を集めています。全世界で1500万人を超える月間利用者を抱え、日本国内ではソフトバンクが提携し、契約者向けにAI検索サービスを提供しています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 設立年 | 2022年 |
| 設立者 | 米オープンAIの技術者 |
| 主な出資者 | ジェフ・ベゾス氏、米エヌビディアなど |
| 月間利用者数(全世界) | 1500万人超 |
| 日本での提携 | ソフトバンク(契約者向けAI検索サービス提供) |
各新聞社が提訴に踏み切った理由
読売新聞グループ本社は、2025年8月7日に、パープレキシティに対して東京地方裁判所に提訴したと発表しました。
これは、AI検索を巡り日本のメディアが著作権侵害で訴訟を起こす初の事例とみられています。読売新聞は、パープレキシティによる記事の無断使用が著作権を侵害しているとして、約21億6800万円の損害賠償などを求めています。
報道によると、訴状では、パープレキシティは2025年2月から6月にかけて、読売新聞オンラインに掲載された約12万本(11万9467本)の記事情報を無断で「取得・複製」し、さらにその情報をもとに生成した類似性のある文章や画像を含む内容を利用者に「送信」したと主張されているようです。
この行為について、読売新聞は、著作権法が定める「複製権」と「公衆送信権」を侵害していると主張しています。
また、パープレキシティのAI検索サービスは、利用者が参照元のウェブサイトを訪れることなく情報を得られる「ゼロクリックサーチ」という特性を持っています。
読売新聞は、このゼロクリックサーチによって、本来ウェブサイトへのアクセスから得られるはずの広告収益などが失われ、営業上の利益を侵害されたとも訴えています。損害賠償の請求に加え、読売新聞はデータ収集事業者を含むサードパーティーによる記事の複製差し止めも求めています。
読売新聞グループ本社広報部は、本件訴訟にあたり、自社のコンテンツに対する権利保護と、報道の質の維持に対する強い姿勢を示しています。
著作権侵害の核心:複製権と公衆送信権
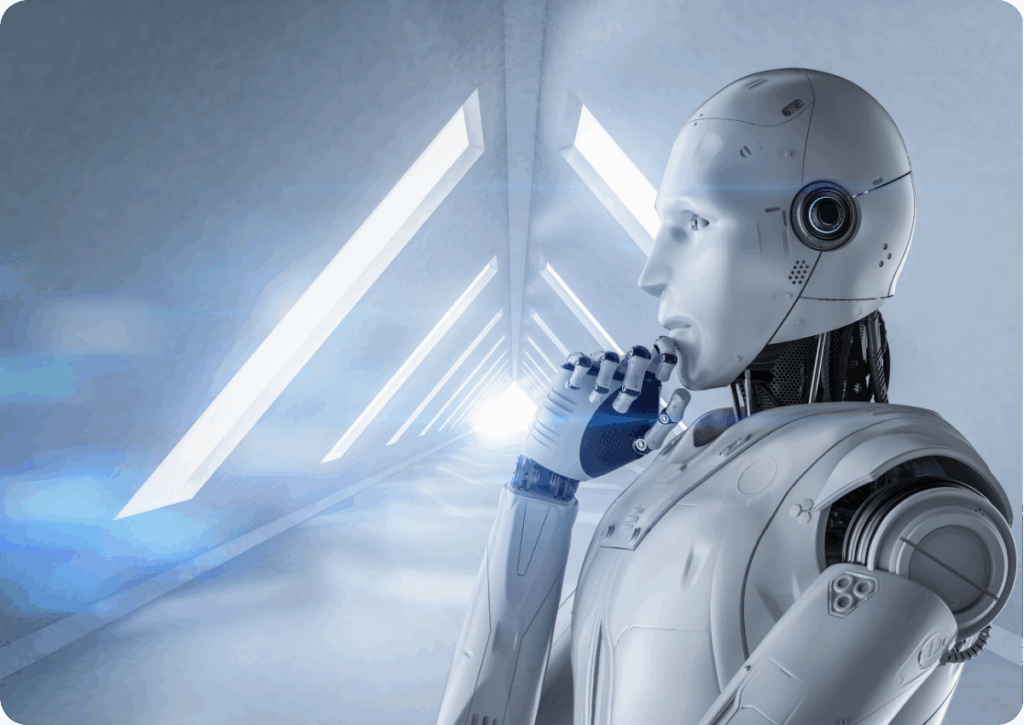
各新聞社がAI検索サービス「パープレキシティ」を提訴した今回の訴訟において、その法的根拠の中心にあるのが、著作権法で定められた「複製権」と「公衆送信権」の侵害です。生成AIの技術が進化する中で、これらの権利がどのように解釈され、適用されるかが、今後のデジタルコンテンツのあり方を大きく左右する重要な争点となっています。
生成AIの仕組みと、生成AIと著作権の関係については、以下の法律記事でも解説していますので、参考までにご参照ください。
生成AIによる記事の「取得・複製」が問われる複製権
著作権法における複製権とは、著作物をそのまま、または形を変えて「複製」する行為を排他的にコントロールできる権利を指します。典型的には、書籍のコピー、写真のスキャン、デジタルデータのダウンロードなどがこれに該当します。
第三十条の四 (著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
今回の訴訟で各新聞が主張しているのは、各新聞記事の情報を「取得・複製」した行為が、この複製権を侵害しているという点です。
・本件の複製権に関する焦点は、以下の二点となることが予想されます。
- AIによる学習目的でのコンテンツ収集が、著作権者の許可なく行われた「無断複製」に該当するか
- 当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的があるか
生成AIが学習のためにインターネット上の大量のコンテンツを収集し、自身のデータベースに取り込む行為が、法的に「複製」と見なされるかどうかが問われています。
また、「複製」に関して原則は、上記の著作権法第30条の4の適用があり許可されています。しかし、蓄積され、AIに入力されている著作物と同一類似の著作物を生成する目的も併存している場合は適用除外となります。
要約・生成コンテンツの「送信」が問われる公衆送信権
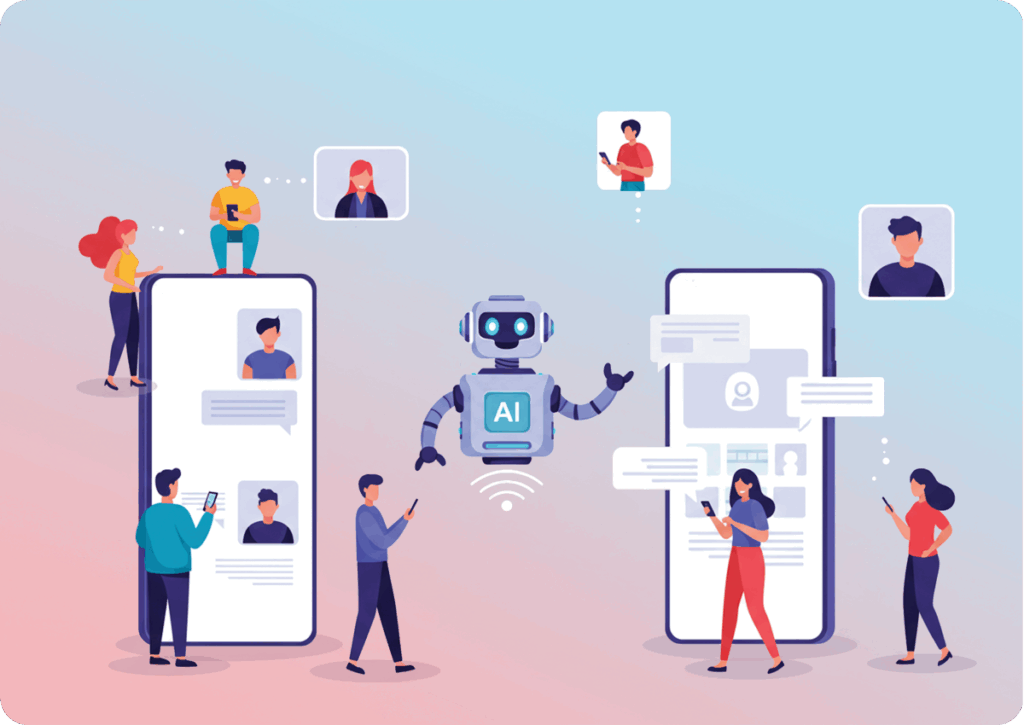
一方、公衆送信権とは、著作物を公衆に向けて「送信」する行為を排他的にコントロールできる権利です。インターネットを通じたコンテンツの配信、テレビやラジオ放送などが典型的な例として挙げられます。
第23条 (公衆送信権等)
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
各新聞社は、パープレキシティが複製した記事情報をもとに、「類似性のある文章や画像を含む内容を作成して利用者に送信」した行為が、公衆送信権の侵害にあたると主張しています。
AI検索サービスは、元の記事を要約したり、情報を再構成したりして、ユーザーに直接その結果を提供します。この行為が、元の著作物の実質的な内容を伴って公衆に提供される場合、著作権者の許諾なく行われれば公衆送信権の侵害となり得ます。
特に、AIが生成したコンテンツが元の記事と酷似していたり、その本質的な部分を抽出して提供したりするケースでは、この権利侵害の可能性が高まります。
著作権法におけるこれらの権利の重要性
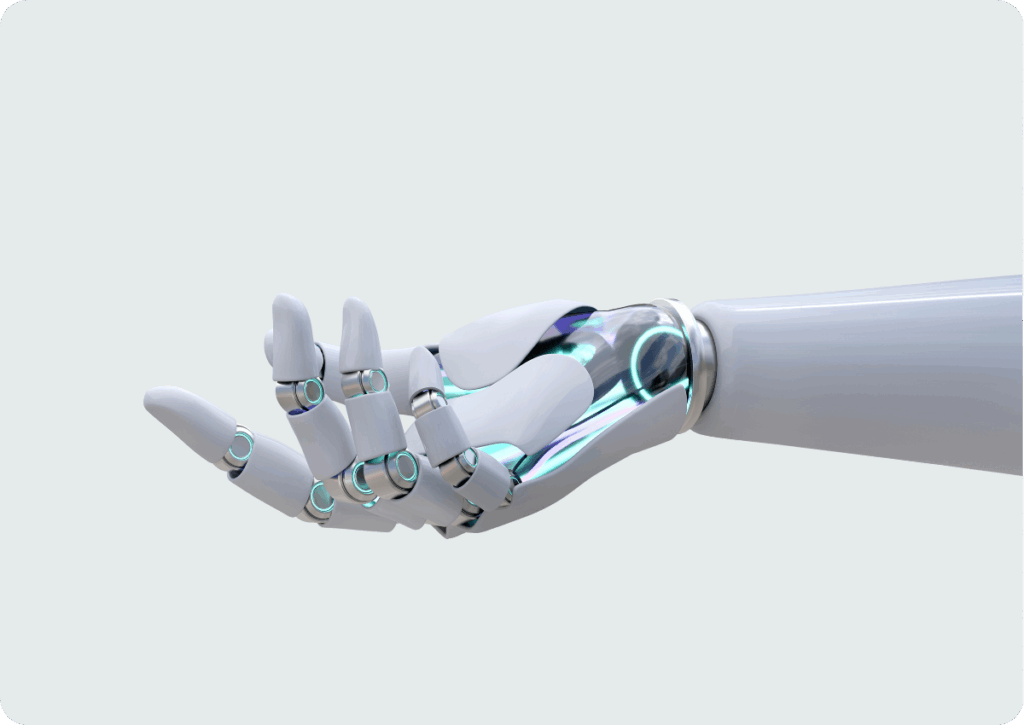
複製権と公衆送信権は、著作権法の中でも特に重要な権利であり、コンテンツ制作者がその創造的な活動によって得た成果を保護し、経済的な対価を得るための基盤となっています。
読売新聞グループ本社は、今回の提訴に際し、「多大な労力と費用をかけて取材をした成果である記事などの著作物が大量に取得・複製され、生成AIによるサービスに利用されていた事実は看過できない。このような『ただ乗り』を許せば、取材に裏付けられた正確な報道に負の影響をもたらす」とコメントしています。
これは、複製権や公衆送信権が適切に保護されない場合、コンテンツ制作者の努力が報われず、ひいては社会全体の情報流通や文化の発展に深刻な悪影響を及ぼすという強い懸念を示しています。
複製権と公衆送信権の比較と生成AIとの関連性
| 権利の種類 | 定義 | 生成AIとの主な関連性 | 読売新聞の主張 (報道による) |
|---|---|---|---|
| 複製権 | 著作物をそのまま、または形を変えてコピーする権利。 | AIが学習データとしてコンテンツを「取得・複製」する行為。 | パープレキシティが読売新聞の記事11万9467本を無断で取得・複製したこと。 |
| 公衆送信権 | 著作物を公衆に送信(インターネット配信など)する権利 | AIが生成した要約やコンテンツをユーザーに「送信」する行為。 | パープレキシティが複製記事から生成した類似文章や画像をユーザーに提供したこと。 |
生成AIの仕組みと、生成AIと著作権の関係については、以下の法律記事でも解説していますので、参考までにご参照ください。
「ゼロクリックサーチ」が引き起こす営業妨害
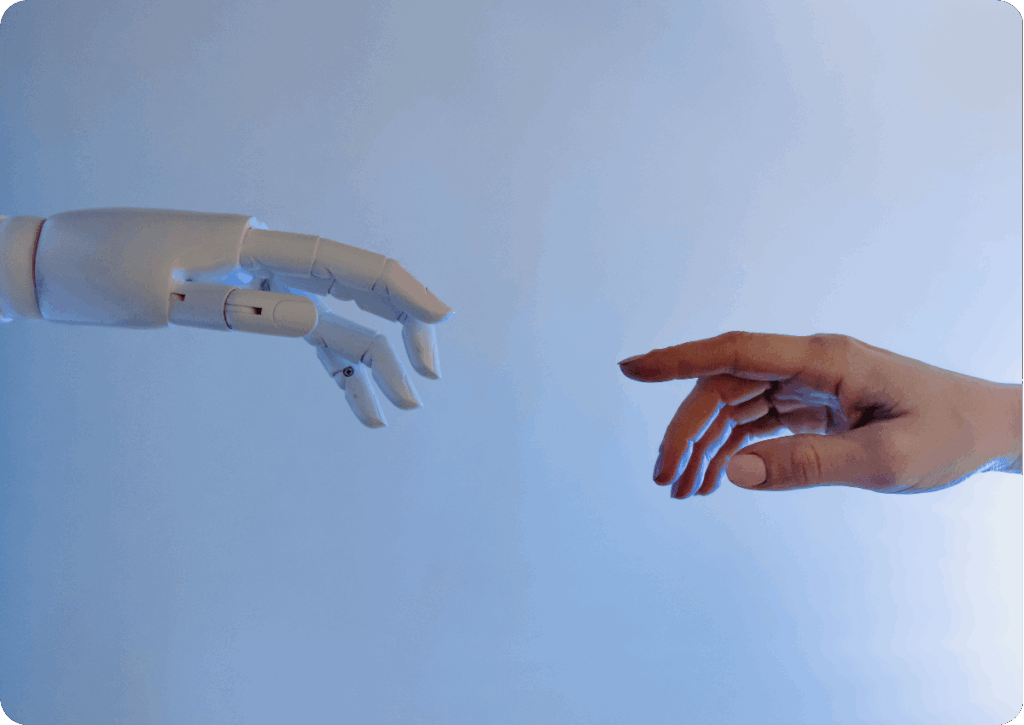
ユーザーの利便性と情報源への影響
「パープレキシティ」のようなAI検索は、ユーザーが検索結果ページから直接、要約された回答や情報を得られる「ゼロクリックサーチ」という体験を提供します。
これは、従来の検索エンジンが提示するリンクをクリックして情報源のウェブサイトに遷移する手間を省き、ユーザーの利便性を飛躍的に向上させるものです。
しかし、このゼロクリックサーチは、情報源となるオリジナルコンテンツの提供者、すなわちメディアやコンテンツ制作者に深刻な影響を及ぼします。
ユーザーが元のウェブサイトを訪問する必要がなくなるため、ウェブサイトへのトラフィックが激減します。
このトラフィックの減少は、後述するコンテンツ制作者の経済的損失に直結する大きな問題です。
従来の検索と生成AI検索(ゼロクリックサーチ)の比較
従来の検索と生成AI検索(ゼロクリックサーチ)が、ユーザー行動とコンテンツ提供者に与える影響の違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | 従来のキーワード型検索 | 生成AI検索(ゼロクリックリサーチ) |
|---|---|---|
| ユーザーの行動 | 検索結果から情報源サイトへ遷移し、詳細情報を得る | 検索結果ページで要約された回答を直接得る |
| 情報源サイトへの影響 | ウェブサイトへのトラフィック増加、ページビュー増加 | ウェブサイトへのトラフィック減少、ページビュー減少 |
| コンテンツ提供者の収益 | 広告収入、サブスクリプション収入、ブランド価値向上 | 広告収入の減少、サブスクリプション収入への影響、ブランド価値の希薄化 |
| 情報の深掘り | サイト内で関連情報や詳細な背景を確認可能 | 要約情報が主で、深掘りには元のサイト訪問が必要 |
| 著作権侵害のリスク | リンク提示が主で、引用元明示が基本 | コンテンツの無断複製・要約・送信による著作権侵害のリスク |
生成AIと著作権問題の世界的動向
国内初の訴訟が示す意味
読売新聞が米新興パープレキシティを東京地裁に提訴したことは、日本のメディアが生成AIによる著作権侵害に対して法的措置に踏み切った初めての事例とみられています。
この国内初の訴訟は、今後の日本の生成AIサービス開発企業や、コンテンツホルダー、さらには一般ユーザーに対して、生成AIの利用における著作権の重要性と、適切な利用ルールの確立が喫緊の課題であることを強く認識させる契機となるでしょう。
特に、ユーザーが参照元のウェブサイトを訪れない「ゼロクリックサーチ」による営業妨害の主張は、メディアのビジネスモデルに与える影響という点で、大きな注目を集めています。
海外メディアの先行事例:WSJの動き
生成AIと著作権の問題は日本に限らず、世界中で議論され、訴訟も相次いでいます。読売新聞の提訴前にも、海外の主要メディアが同様の懸念から法的措置を取っています。
最も注目される事例の1つが、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)を傘下に持つダウ・ジョーンズが2024年10月にパープレキシティを提訴したケースです。ダウ・ジョーンズは、著作権侵害を理由に損害賠償や記事の利用停止、データの廃棄などを求めています。
また、これ以外にも、著名なメディア企業が生成AI企業に対して訴訟を起こしています。例えば、米ニューヨーク・タイムズは2023年12月、OpenAIとマイクロソフトを相手取り、自社の数百万の記事が無断でAIのトレーニングに使用され、著作権を侵害しているとして提訴しました。この訴訟では、AIが生成したコンテンツがニューヨーク・タイムズの記事と酷似している例も示され、大きな波紋を呼んでいます。
コンテンツの「取得・複製」が問われる複製権や、「要約・生成コンテンツの送信」が問われる公衆送信権といった著作権の基本的な権利が、生成AIの技術によってどのように解釈され、適用されるのかが、今後の国際的な動向の焦点となるでしょう。
以下に、主要な海外の訴訟事例の一部を示します。
| 提訴主体 | 提訴対象 | 主な主張 | 提訴時期(報道時期) |
|---|---|---|---|
| ダウ・ジョーンズ(ウォール・ストリート・ジャーナル傘下) | パープレキシティ | 著作権侵害(記事の無断利用)、損害賠償、記事利用停止、データ廃棄 | 2024年10月 |
| ニューヨーク・タイムズ | OpenAI、マイクロソフト | 著作権侵害(記事のAI学習利用、類似コンテンツ生成)、損害賠償 | 2023年12月 |
| その他複数の作家、アーティスト | OpenAI、Stability AI、Midjourneyなど | 著作権侵害(作品のAI学習利用)、損害賠償 | 2023年以降継続的に発生 |
まとめ
本記事では、ニュースや時事問題について、法律の観点から解説をする「プロトキ」の第11回として、「AI検索で記事が無断使用?読売新聞に続き日経新聞と朝日新聞、生成AIの運営企業を著作権侵害で日本初の提訴へ」のニュースを解説していきました。
簡単にまとめると以下のような内容です。
- 読売新聞社は複製権と公衆送信権、ゼロクリックリサーチによる営業妨害に基づいて国内初の具体的な訴訟提起をした
- その後、日本経済新聞社と朝日新聞社も同様に訴訟を提起している
- 生成AIによるコンテンツ収集は複製権と公衆送信権の侵害にあたる可能性がある
- ゼロクリックリサーチによって利用者が元サイトを訪れないことは営業妨害に当たる可能性がある
- 海外では生成AIと著作権に関する訴訟が複数提起されている
次回以降も、「プロトキ」では、ニュースや時事問題についてプロスパイア法律事務所の専門家が法的観点から解説をしていきます。
次回の更新をお楽しみに。

プロスパイア法律事務所
代表弁護士 光股知裕
損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。