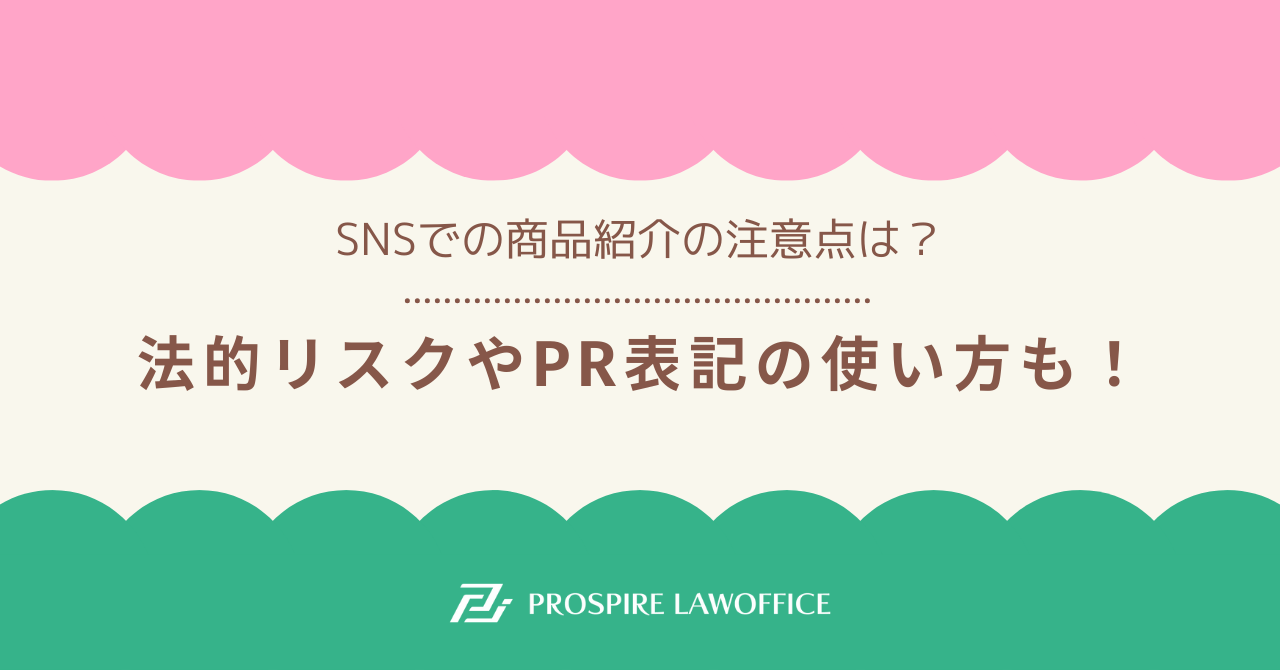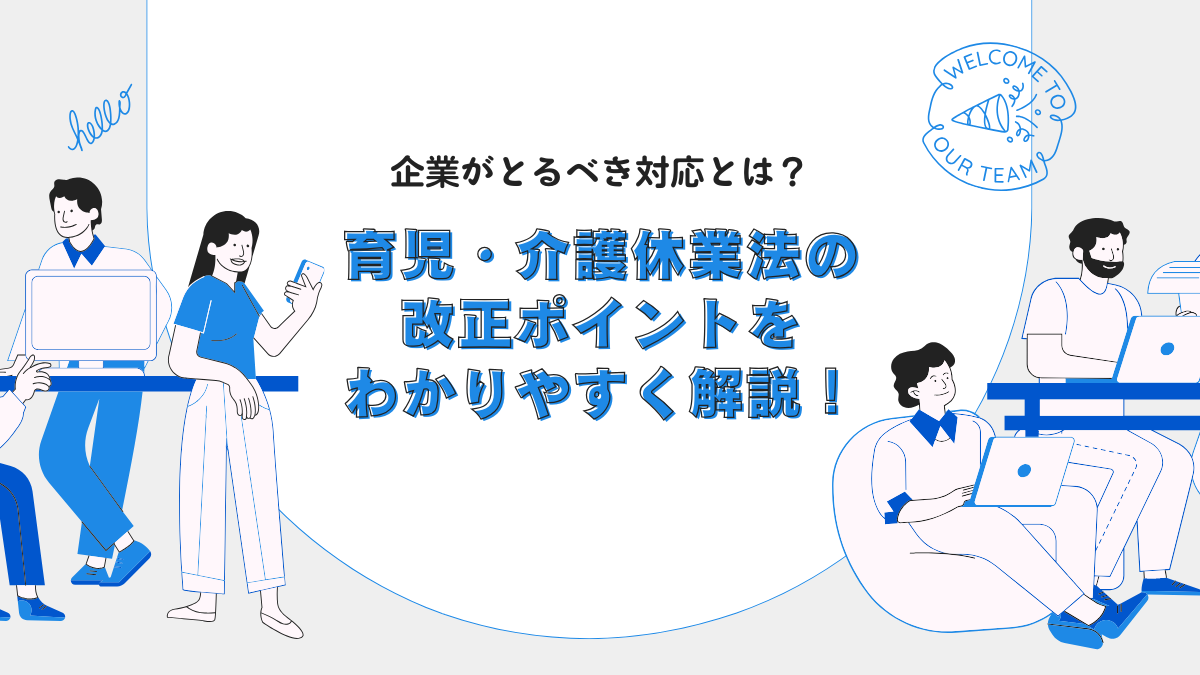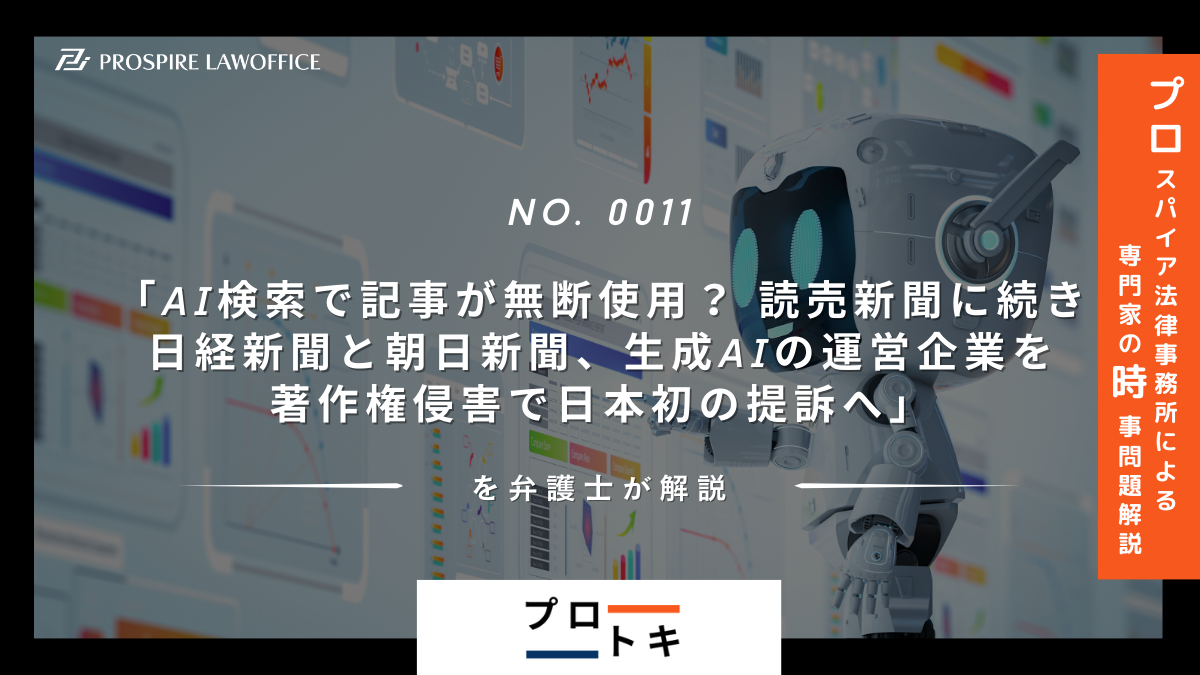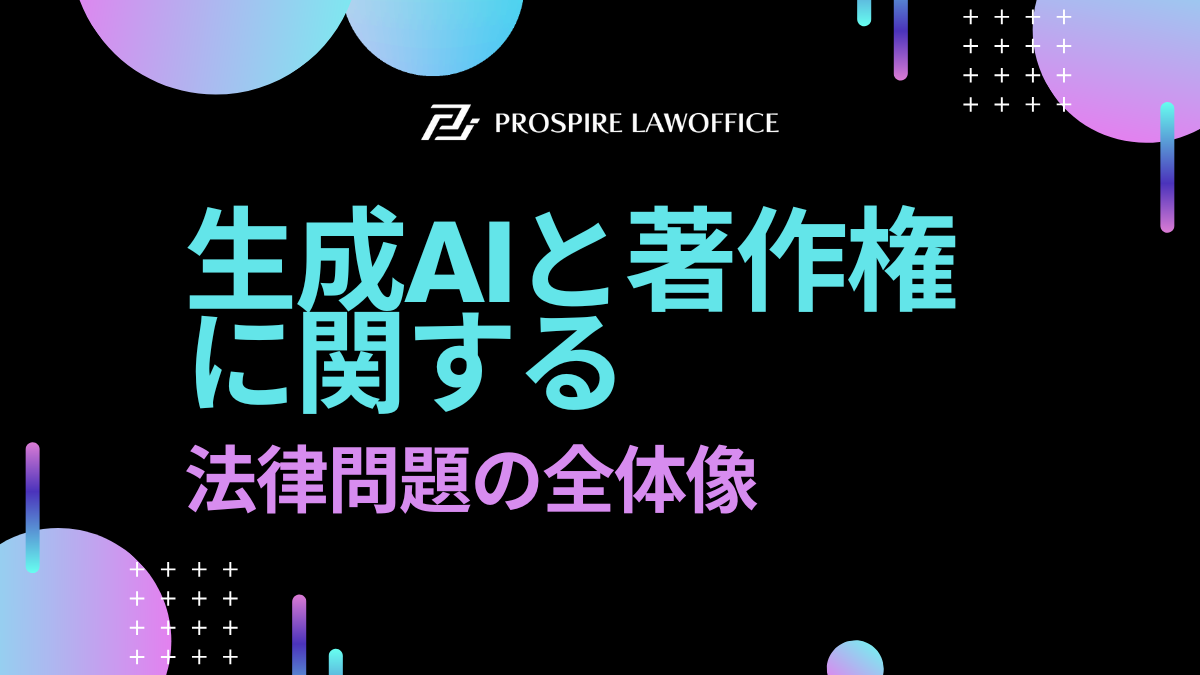「遺言書の書き方って難しそう…」「書いたのに効力がないと困る…」そんな不安を抱えていませんか?
この記事では、遺言書の書き方と効力がどのように結びついているのか、相続トラブルを回避するためのポイントを分かりやすく解説します。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言それぞれの書き方や注意点、よくある誤解、そして無効にならないための対策まで、専門家の視点を取り入れながら詳しく説明。
この記事を読めば、あなたに最適な遺言書の書き方が分かり、安心して将来設計を進めることができるでしょう。
遺言書の書き方によって変わる?遺言の効力

遺言書は、故人の意思に基づいて財産を分配するための重要な書類です。しかし、書き方を間違えると、せっかく作成した遺言書が無効になってしまう可能性があります。
遺言の効力は、遺言書の書き方、すなわち方式によって大きく左右されます。適切な方式で作成された遺言書のみが法的な効力を持ち、故人の意思を実現することができます。
そのため、遺言書を作成する際には、それぞれの方式の特徴や注意点、そしてどのような効力の違いが生じるのかを理解しておくことが重要です。
遺言書の効力発生の時期
遺言書の効力は、遺言者が亡くなった時点で発生します。つまり、遺言書を作成した時点では、まだ効力は発生していません。遺言者は、生前に何度でも遺言書の内容を変更したり、撤回したりすることができます。
ただし、新しい遺言書を作成した場合、以前の遺言書は自動的に無効になるわけではありません。後の遺言書が有効であれば、以前の遺言書は効力を失います。複数の遺言書が存在する場合、どの遺言書が有効か、どの部分が有効かなどを慎重に判断する必要があります。
遺言の方式と効力
民法で定められている遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれの方式には、メリット・デメリットがあり、作成の手軽さや費用、そして効力にも違いがあります。どの方式を選ぶかは、遺言者の状況や希望に合わせて決定する必要があります。
| 方式 | 書き方 | メリット | デメリット | 効力 |
|---|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 全文、日付、氏名を自書し、押印する | 費用がかからない、手軽に作成できる | 方式の不備で無効になりやすい、紛失・改ざんの恐れがある | 有効な自筆証書遺言であれば、他の方式の遺言と同様の効力を持つ |
| 公正証書遺言 | 公証役場で証人2人以上の立会いのもと、公証人に内容を伝え、作成してもらう | 無効になりにくい、紛失・改ざんの恐れがない | 費用がかかる、手続きが複雑 | 最も確実な効力を持つ |
| 秘密証書遺言 | 遺言書を作成し、封をして、公証役場で証人2人以上の立会いのもと、公証人に提出する | 内容を秘密にできる | 費用がかかる、手続きが複雑、方式の不備で無効になりやすい | 有効な秘密証書遺言であれば、他の方式の遺言と同様の効力を持つ |
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を自書し、押印する必要があります。費用がかからず、手軽に作成できることがメリットです。ただし、民法で定められた方式を厳格に守らなければ無効となる可能性が高く、紛失や改ざんの恐れもあります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立会いのもと、公証人に内容を伝え、作成してもらう方式です。費用はかかりますが、公証人が作成するため、無効になりにくく、紛失や改ざんの恐れもありません。最も確実な効力を持つ遺言の方式と言えます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言書自体を自分で作成し、封をして、公証役場で証人2人以上の立会いのもと、公証人に提出する方式です。内容を秘密にできることがメリットですが、費用がかかり、手続きが複雑です。また、方式の不備で無効になる可能性もあります。なお、秘密証書遺言が無効でも、中身が自筆証書遺言の要件を満たす場合であれば、自筆証書遺言としては有効となります。
遺言書の種類と書き方
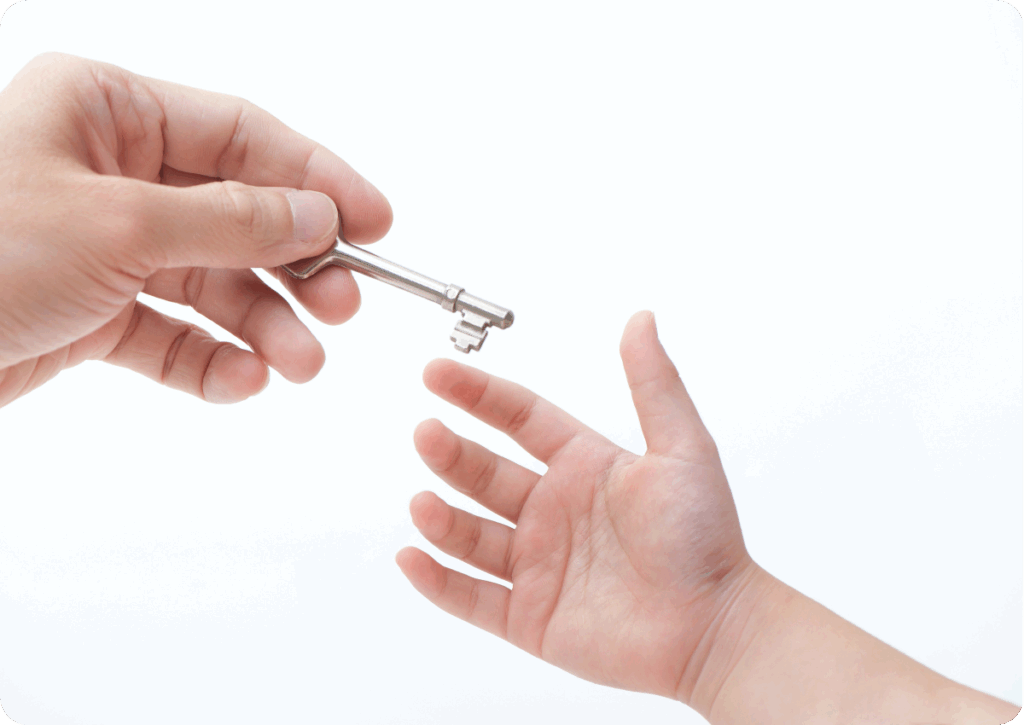
遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれ作成方法やメリット・デメリットが異なるため、自身の状況に合った方法を選択することが重要です。
自筆証書遺言の書き方と注意点
自筆証書遺言は、費用をかけずに手軽に作成できるというメリットがあります。しかし、方式不備による無効のリスクも高いため、注意が必要です。
全文自書であること
自筆証書遺言は、本文、日付、氏名すべてを自分で手書きする必要があります。パソコンやワープロで作成したものは無効です。代筆も認められません。財産目録については、自筆でなくても構いませんが(2020年7月10日施行の改正民法による)、各ページに署名押印が必要です。
日付の記入
作成日を明確にするため、必ず日付を記入してください。「令和5年10月1日」のように、元号と西暦のどちらかで統一して記入しましょう。「10/1」のような省略した書き方は無効になる可能性があります。
署名と押印
氏名は、戸籍に登録されているものと同一である必要があります。実印である必要はありませんが、印鑑登録をしている方は実印を使用することをおすすめします。
公正証書遺言の書き方と注意点
公正証書遺言は、公証役場で作成するため、方式不備による無効のリスクが低いというメリットがあります。ただし、費用と手間がかかるというデメリットもあります。
証人2人以上の立ち会い
公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立ち会いが必要です。証人には、未成年者、推定相続人のほか、受遺者、その配偶者、直系血族はなることができません。
公証役場での作成
公証役場で、遺言の内容を公証人に口述します。公証人が筆記し、読み聞かせた後、署名押印します。
原本の保管
原本は公証役場で保管されます。紛失や改ざんの心配がありません。
秘密証書遺言の書き方と注意点
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にできるというメリットがあります。ただし、手続きが複雑で、方式不備による無効のリスクも高いため、注意が必要です。
遺言書の封入と署名押印
遺言書を作成し、封筒に入れて封をします。封じ目に署名押印します。自筆でもワープロで作成したものでも構いません。
公証役場での手続き
封をした遺言書を公証役場に持参し、証人2人以上の立ち会いのもと、遺言書を提出した旨を申述します。公証人が遺言書の表面に日付などを記載し、署名押印します。
遺言書の種類とそれぞれの作成方法、注意点についてまとめました。
| 種類 | メリット | デメリット | 書き方 |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 費用がかからない、手軽に作成できる | 方式不備で無効になる可能性が高い、紛失・改ざんの恐れがある | 全文自書、日付、氏名の記入、署名押印 |
| 公正証書遺言 | 方式不備で無効になる可能性が低い、紛失・改ざんの恐れがない | 費用がかかる、証人2人必要、手続きが煩雑 | 公証役場で口述、証人2人の立ち会い |
| 秘密証書遺言 | 遺言の内容を秘密にできる | 手続きが複雑、方式不備で無効になる可能性が高い | 遺言書を封入し署名押印、公証役場で手続き |
遺言書の効力に関するよくある誤解

遺言書を作成すれば全てが解決すると考えている方もいるかもしれませんが、実際にはいくつかの誤解が存在します。この章では、遺言書の効力に関してよくある誤解を解説し、正しい理解を深めていただくことを目的としています。
遺言書があれば全てが解決するわけではない
遺言書は、故人の意思を尊重し、相続手続きを円滑に進めるための重要なツールです。しかし、遺言書の存在だけで全ての相続問題が解決するわけではありません。
例えば、以下のようなケースでは、遺言書の内容が実現されない可能性があります。また、受遺者が先に死亡していた場合は、遺贈は効力を生じません。
| ケース | 説明 |
|---|---|
| 遺留分侵害 | 遺言書の内容が、法定相続人の遺留分を侵害している場合、遺留分侵害額請求によって、遺留分相当額の金銭を請求される可能性があります。 |
| 遺言書の無効 | 遺言書に形式的な不備があったり、作成時の本人の意思能力に問題があったりする場合、遺言書自体が無効と判断される可能性があります。 |
| 債務の存在 | 故人に多額の債務があった場合、相続財産はまず債務の返済に充てられます。そのため、遺言書で指定された通りの相続ができない場合があります。 |
遺言書は、相続手続きにおける重要な要素ですが、万能ではありません。 相続トラブルを避けるためには、遺言書の作成だけでなく、相続人とのコミュニケーションや専門家への相談も重要です。
法定相続分を無視した遺言は必ず無効になるわけではない
法定相続分とは、民法で定められた相続人の相続分の割合のことです。遺言書によって法定相続分と異なる割合で相続させることは可能です。法定相続分を無視した遺言を作成しても、必ずしも無効になるわけではありません。 ただし、この場合、遺留分を侵害している可能性があります。
遺留分とは
遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる財産の割合のことです。遺言によって相続分が減らされた場合でも、この遺留分は保障されています。遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、侵害された部分を金銭として請求できる権利のことです。この請求が認められると、遺言の内容が一部変更され、遺留分が保障されることになります。
遺言書で法定相続分と異なる配分をする場合には、遺留分について十分に理解し、将来のトラブルを避けるように配慮することが重要です。 必要に応じて、専門家(弁護士や司法書士など)に相談することをお勧めします。
相続トラブルを回避するための遺言書の書き方

遺言書は、あなたの大切な財産を、あなたの意思に基づいて分配するための重要な手段です。しかし、書き方を間違えると、せっかく作成した遺言書が無効になってしまったり、相続人間でトラブルが発生してしまう可能性があります。大切な家族のために、そしてあなたの意思を確実に実現するために、遺言書作成のポイントをしっかりと押さえましょう。
遺言書作成の目的を明確にする
遺言書を作成する目的を明確にすることは、相続トラブルを回避するための第一歩です。誰に何を、どのくらいの割合で相続させたいのか、具体的に考えてみましょう。例えば、「自宅は長男に、預貯金は均等に分割する」といったように、具体的な分配方法を明確にすることで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
相続人の状況を把握する
遺言書を作成する際には、相続人の状況を把握しておくことも重要です。相続人の人数、年齢、職業、経済状況などを考慮することで、より適切な遺言書を作成することができます。例えば、既に経済的に自立している相続人と、そうでない相続人がいる場合、それぞれの状況に応じて相続分を調整する必要があるかもしれません。また、認知症の相続人がいる場合は、その方の生活を保障するための配慮も必要です。
専門家への相談
遺言書の作成は、法律的な知識が必要となる複雑な作業です。少しでも不安な点があれば、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、あなたの状況に合わせて適切なアドバイスを提供し、トラブルのない遺言書作成をサポートしてくれます。複雑な家族関係や財産状況の場合、専門家のサポートは特に重要です。
遺言書作成に関する相談窓口としては、日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会などが挙げられます。これらの団体では、遺言書作成に関する相談を受け付けており、専門家を紹介してくれる場合もあります。
| 相談窓口 | 内容 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 日本弁護士連合会 | 法律相談 | 各地域の弁護士会にお問い合わせください |
| 日本司法書士会連合会 | 法律相談、書類作成支援 | 各地域の司法書士会にお問い合わせください |
| 税理士 | 相続税に関する相談 | 日本税理士会連合会 |
円満な相続を実現するためにも、遺言書作成の際は、これらのポイントを踏まえ、必要に応じて専門家のサポートを受けるようにしましょう。
遺言書作成時に知っておきたい付言事項

遺言書には、相続財産の分配方法以外にも、様々なことを記載することができます。これらを付言事項といいます。付言事項は法的拘束力を持つものと持たないものがあります。法的拘束力がない付言事項であっても、遺言者の意思を伝える大切な役割を果たします。ここでは、代表的な付言事項について解説します。
遺言執行者について
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。遺言で指定することができます。遺言執行者を指定することで、相続手続きがスムーズに進みやすくなります。
遺言執行者には、以下のような役割があります。また、遺言執行者がいる場合、遺贈の履行はその者にしかできません。
- 相続財産の調査・管理
- 相続人の確定
- 遺産分割協議の進行
- 相続財産の分配
- 各種名義変更手続き
遺言執行者には、相続人や弁護士、司法書士、信託銀行などを指定することができます。また、相続人や受遺者でも、未成年または破産者でなければ遺言執行者になることができます。相続人間で紛争が予想される場合や、手続きが複雑な場合は、弁護士や司法書士などの専門家を遺言執行者に指定することをおすすめします。
また、遺言執行者には報酬を支払うことができます。報酬額は遺言で指定するか、遺言執行者と相続人の間で協議して決定します。報酬額の目安は、遺産総額の1~5%程度です。
相続財産の特定
遺言書で相続財産を分配する際には、どの財産を誰に相続させるかを具体的に記載することが重要です。曖昧な表現は、後々のトラブルの原因となる可能性があります。
例えば、「預貯金」とだけ記載するのではなく、「〇〇銀行の普通預金口座(口座番号:〇〇)」のように具体的に記載しましょう。
不動産についても、所在地や地番などを明確に記載する必要があります。また、不動産の登記事項証明書などを添付すると、より明確になります。
以下は、相続財産の特定方法の例です。
| 財産の種類 | 特定方法の例 |
|---|---|
| 預貯金 | 金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号 |
| 不動産 | 所在地、地番、家屋番号 |
| 株式 | 銘柄名、証券会社名、口座番号 |
| 動産(自動車など) | 車種、車体番号 |
財産を特定できない場合、遺言が無効になる可能性があります。財産の特定には、注意を払いましょう。
無効な遺言書にならないために
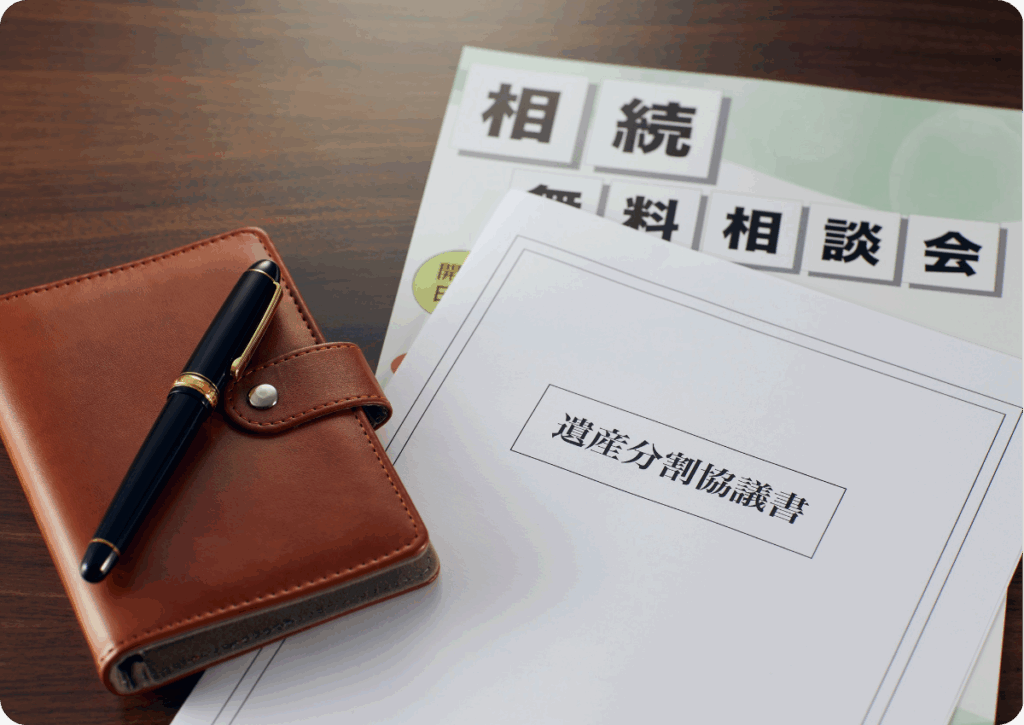
せっかく遺言書を作成しても、方式不備などで無効になってしまうと、あなたの意思は反映されません。ここでは、無効な遺言書にならないための注意点と、作成後、修正が必要になった場合の対処法について解説します。
訂正や加筆の方法
自筆証書遺言の場合、訂正は、訂正箇所を明示し、訂正内容の付記・署名・押印が必要です。具体的には、加除訂正には、線を引いて、その箇所に訂正印を押す必要があります。そして、変更内容と変更した日付を記入します。変更部分が複数個所に及ぶ場合や、大幅な書き直しが必要な場合は、新しく書き直すのが安全です。書き損じた遺言書は、破棄するか、無効にする旨を明記して保管しておきましょう。
公正証書遺言の場合、変更や追加は、公証役場で手続きを行います。そのため、変更したい場合は、再度公証役場へ行き、証人2名と共に手続きをする必要があります。
秘密証書遺言の場合、変更したい場合は、一度開封して訂正するか、新たに遺言書を作成し、以前の遺言書を無効にする旨を記載する必要があります。訂正した場合は、再度封をして、公証役場で手続きを行い直す必要があります。
| 遺言書の方式 | 訂正・加筆の方法 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | |
| 公正証書遺言 | 公証役場で手続きを行う。 |
| 秘密証書遺言 | 開封して訂正、再封入し公証役場で手続き。または、新たに遺言書を作成し、以前の遺言書を無効にする旨を記載。 |
証人の選定
公正証書遺言と秘密証書遺言には、証人2人以上の立会いが必要です。証人には、未成年者や、推定相続人、受遺者およびこれらの配偶者、直系血族はなることができません。証人がこれらの要件を満たしていない場合、遺言は無効になってしまいます。また、証人は、遺言の内容を理解できる能力が必要です。証人を選定する際は、これらの点に注意しましょう。
これらの点に注意し、確実な効力を持つ遺言書を作成することで、あなたの意思を確実に伝え、相続トラブルを未然に防ぐことができます。
まとめ

この記事では、遺言書の「書き方」と「効力」について解説しました。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ書き方や注意点が異なります。
自筆証書遺言は手軽に作成できますが、要件を満たしていないと無効になる可能性があるため注意が必要です。
公正証書遺言は費用がかかりますが、専門家のアドバイスを受けながら作成でき、最も確実な方法です。
秘密証書遺言は内容を秘密にできますが、手続きが複雑です。
遺言書を作成する際は、自身の状況に合った方法を選択し、正しい書き方で作成することが重要です。また、遺言書は作成後も、内容の変更や加筆修正が必要になる場合もあります。訂正方法も理解しておきましょう。
さらに、遺言書の作成は、相続トラブルを未然に防ぐための有効な手段となります。将来の不安を解消し、円満な相続を実現するために、この記事を参考に遺言書作成を検討してみてください。

弁護士法人市ヶ谷板橋法律事務所
弁護士 板橋 晃平
都内のワンストップ型総合法律事務所に勤務し、遺産相続、企業法務、不動産案件など幅広い分野の案件を担当。その後、2024年に市ヶ谷板橋法律事務所を設立し、2025年には法人化して弁護士法人市ヶ谷板橋法律事務所と改組。遺産相続・企業法務を中心として業務を行っている。