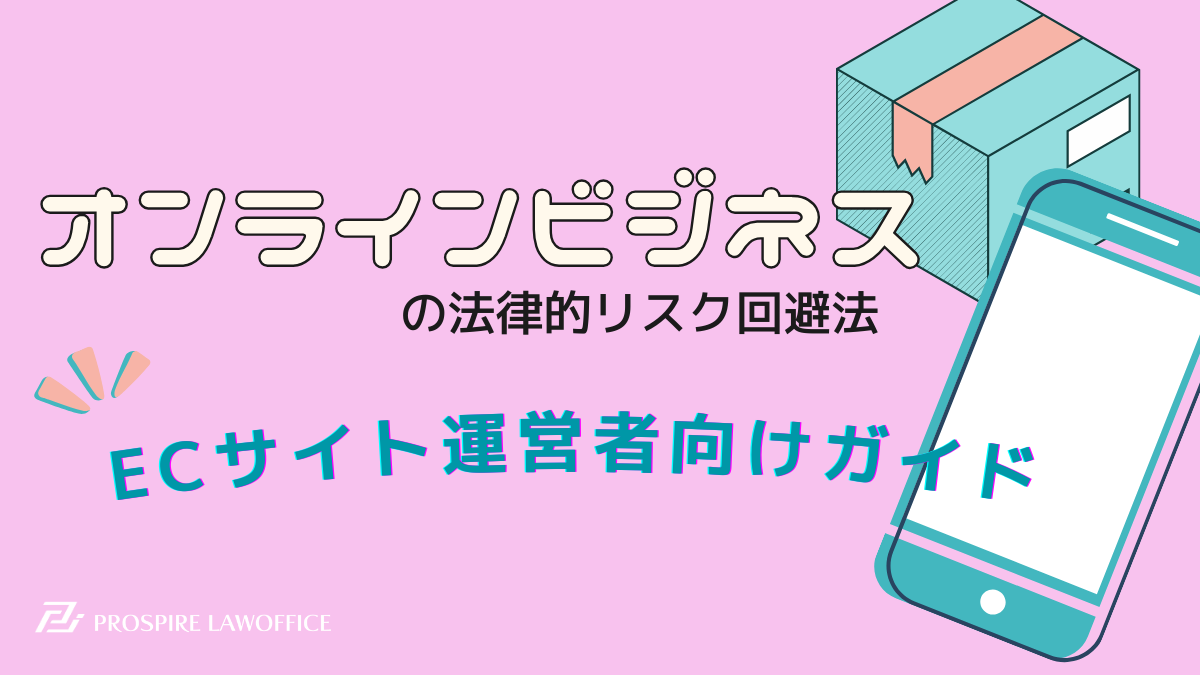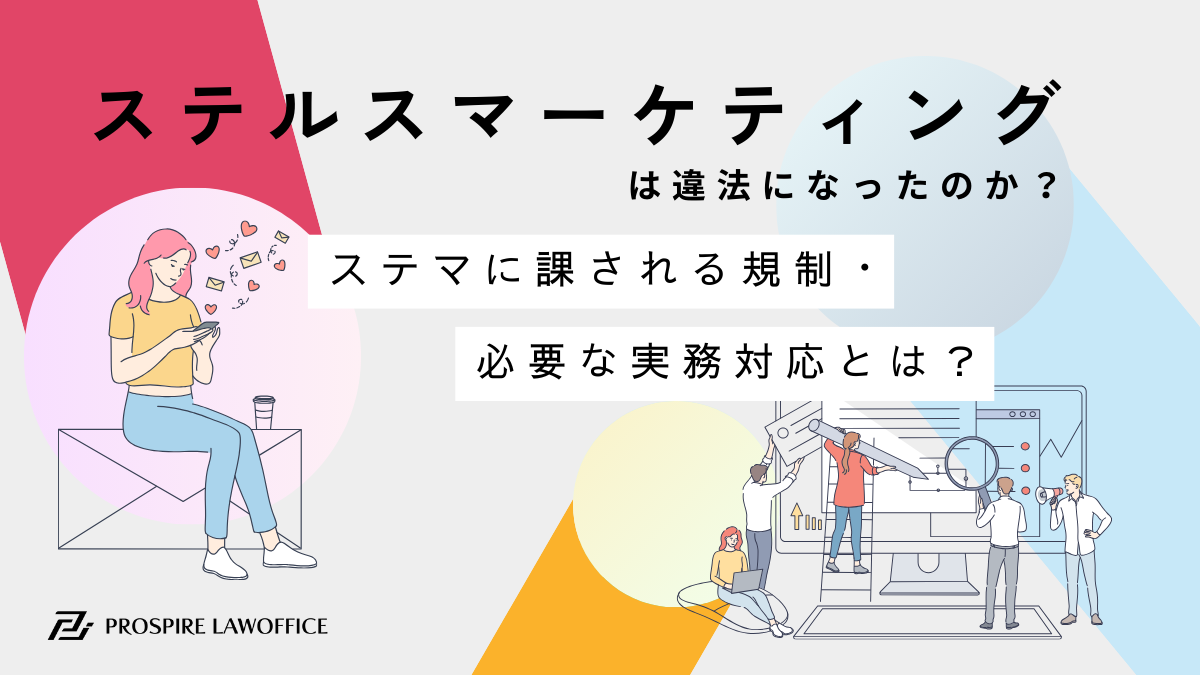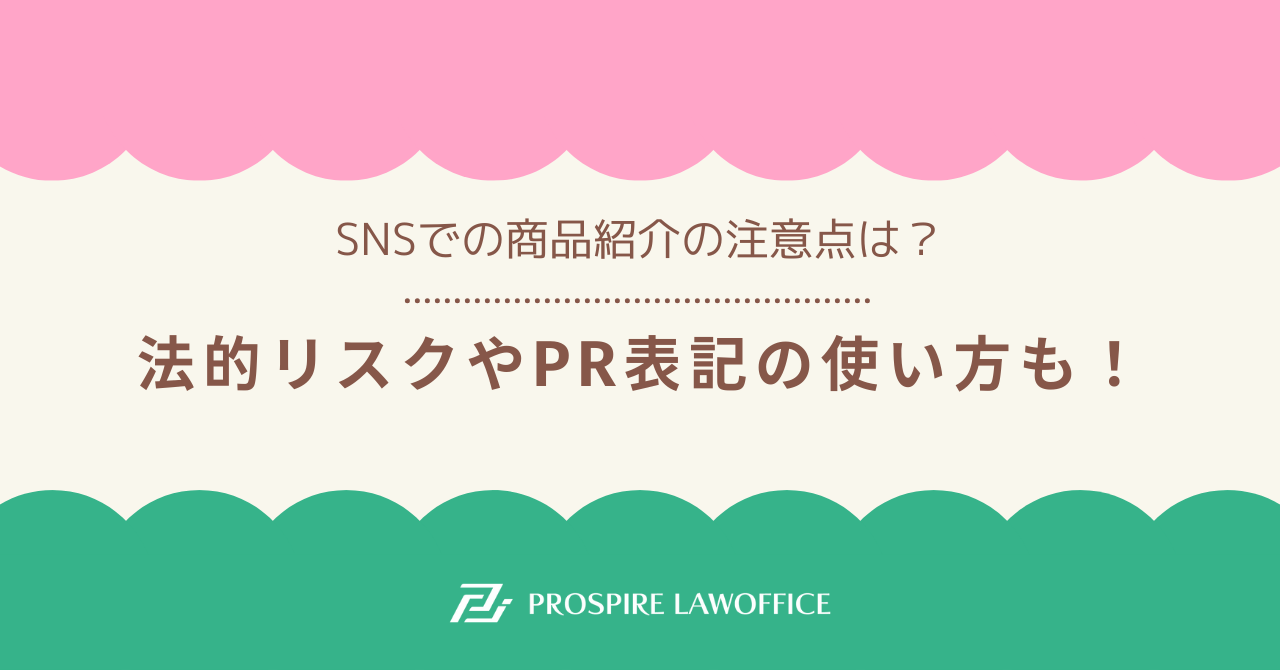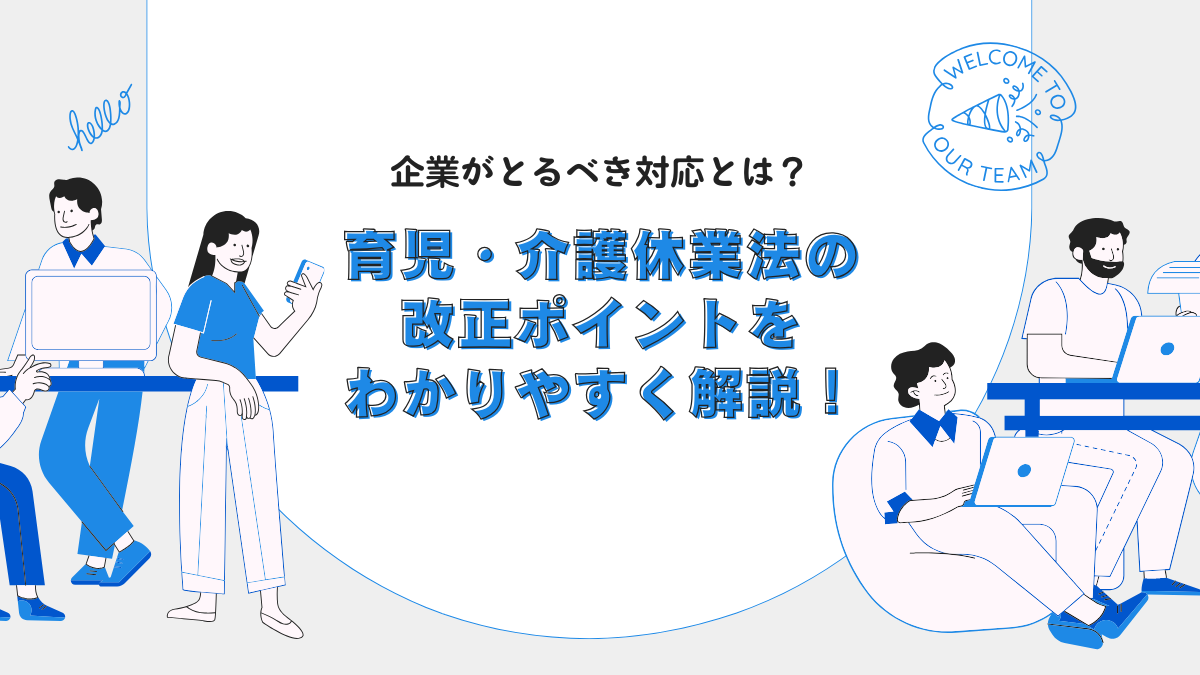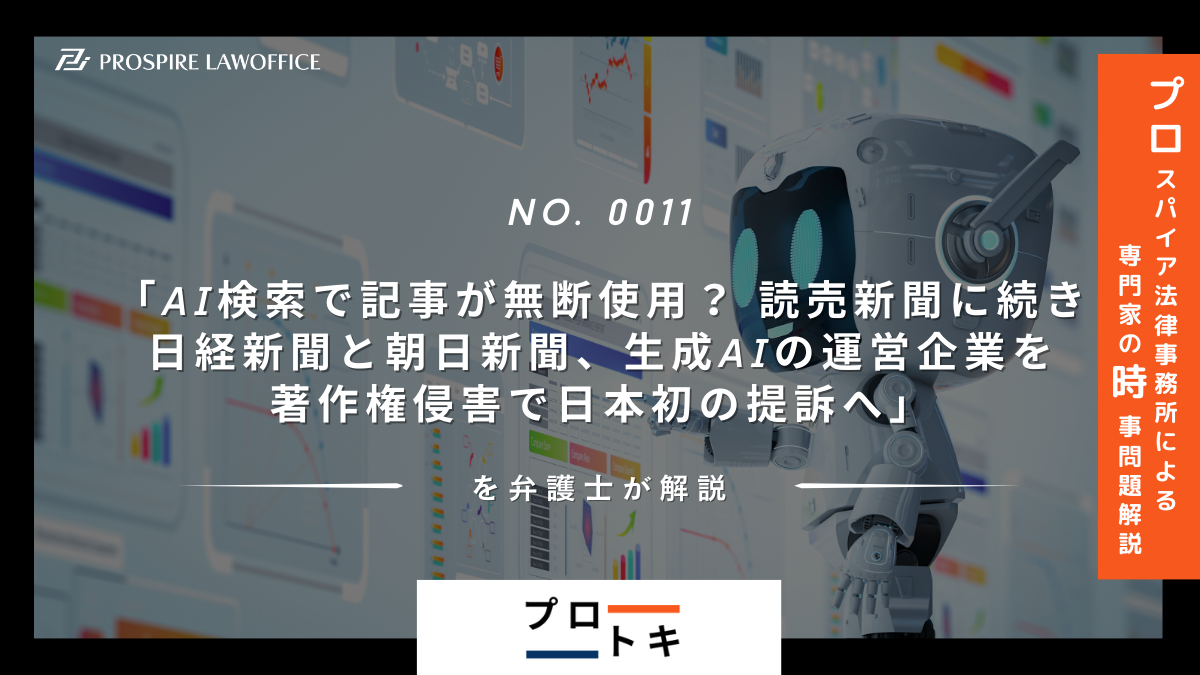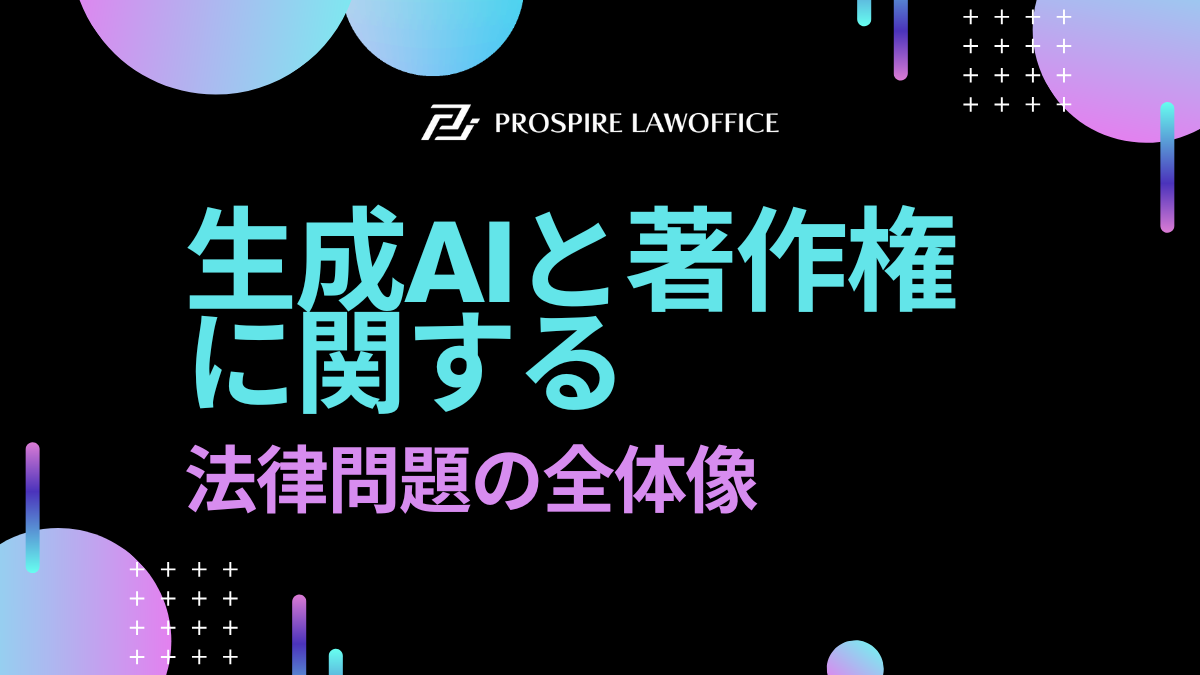近年、インターネットの急速な普及によりインターネットのサイトで手軽に買い物ができるようになりました。こうしたネット上のショッピングサイトはECサイトとも呼ばれ、実店舗を構えなくとも誰でも気軽にサービス・商品の販売をすることができ、大きな広がりを見せています。
しかし、いくら従来よりも手軽に販売・取引ができるようになったといっても、ECサイトの立ち上げ・運営には様々な法令が複雑に関係しており、使い方によっては法律上のトラブルに発展する可能性があります。
そこで今回は、ECサイトの立ち上げ・運営に際して法令上、何を準備しておけばよいのか等の最低限必要な知識は何かについて解説していきます。
音声解説
この記事のテーマと同一内容をラジオ形式で解説しています。 以下から是非ご視聴ください。
他の記事の音声解説は、プロスパイア法律事務所のYouTubeチャンネルからご視聴いただけます。
https://www.youtube.com/@ProspireLawOffice
ECサイトについて
ECサイトとは?
まず、ECサイトとは、インターネット上で商品やサービスを販売するウェブサイトのことで、ECとは「electronic commerce(エレクトロニックコマース=電子商取引)」の略です。
そして、ECサイトには「自社型ECサイト」と、「モール型ECサイト」の2種類があります。
「自社型ECサイト」は企業自身がサイトの運営を行うECサイトを指します。
(例:ユニクロ、無印良品、Apple)
一方、「モール型ECサイト」とは、ショッピングモールの様に1つのECサイト内に複数の店舗が出店している形態のECサイトを指します。
(例:Amazon、楽天、ZOZOTOWN)
モール型ECサイトでは各モールにより出店手順が明確に定められていることが多く、基本的には自社型ECサイトが原則形態となるため、本記事では自社型ECサイトを念頭に解説します。
運営上起こりうるトラブル
多くの方が上記の具体例で挙げたサイトで買い物をしたことがあると思います。その際、「商品の到着が遅れた」「商品が想像と違った」といったトラブルを経験したことはないでしょうか。ECサイトの運営ではこうしたトラブルが頻発しますが、その都度個別に対応していたのでは円滑に業務を執行できないばかりか、新たなトラブルも生み出しかねません。
加えて、ECサイトでの取引を含む電子商取引においては、民法や刑法などの一般法に加え、様々な特別法も適用されるため、発生しうるトラブルの種類は多岐に渡ります。
そこで、将来起こりうるトラブルを想定し、事前に対処法・解決法を画定・明示する必要があります。
ECサイト関係法令
| 略称 | 正式名称 |
| 景品表示法 | (不当景品類及び不当表示防止法) |
| 個人情報保護法 | (個人情報の保護に関する法律) |
| 資金決済法 | (資金決済に関する法律) |
| 通則法 | (法の適用に関する通則法) |
| 電子契約法 | (電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律) |
| 特定商取引法 | (特定商取引に関する法律) |
| 特定電子メール法 | (特定電子メールの送信の適正化等に関する法律) |
| 独占禁止法 | (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) |
| 不正アクセス禁止法 | (不正アクセス行為の禁止等に関する法律) |
| 情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法) | (特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律) |
| 預金者保護法 | (偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な 機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律) |
ECサイトの作成に必要なもの
しかし、事前にトラブルの対処法・解決法を決めるといっても、具体的に何をすればいいのでしょうか。そこで、最低限、以下の2つを作成・表示する必要があります。それぞれについて詳しく見ていきましょう。
・利用規約(定型約款)
・特定商取引法に基づく表記
利用規約について
まず、以下では「利用規約」について解説します。
必要性と目的
利用規約はトラブルを未然に防ぐことや、トラブルの早急な解決のために必要ですが、具体的には以下の3つの目的を意識して作成することが重要です。
① 運営事業者とユーザーの法律関係を明確にすること
- ネット上ではその性質上、相互にコミュニケーションが取りづらく、互いに認識にズレがある場合があります。その際、運営者とユーザーの間にいつ、どのような契約が成立し、いかなる権利・義務が発生するかを明確にすることで両者の円満な関係の維持が図れます。
② ユーザーに対する禁止行為とペナルティの設定
- 悪質なユーザーがいる場合、それを放置すれば様々な人が被害を受ける可能性があります。こうした場合に悪質なユーザーに対抗できるようにしておくことでサイト内の秩序を維持することができます。
③ 責任の範囲を明確にすること
- もし運営者がユーザーに対して損害を被らせてしまった場合、ユーザーとしてはできるだけ手厚い補償を望むでしょう。しかし、いちいちこうした求めに応えるのは現実的でなく、トラブルの早期解決に支障をきたす場合があります。そこで、予め運営者が負う責任の範囲を画定しておくことが必要です。
法的な意味
利用規約は民法上、「定型約款」(民法548条の2)と呼ばれます。
この条文によると、あらかじめ定型的な約款を作成し、個々のユーザーがその定型約款を契約の内容とすることについて同意した場合は、その定型約款の個々の条項についても合意したものとみなされることとされています(民法548条の2第1項)。
つまり、オンラインサービスは不特定多数の者が利用するため、一人ひとりとその都度契約するのではなく、包括的・画一的に契約関係を画定して手間を省こう、ということです。
(定型約款の合意)
第五百四十八条の二 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。)を行うことの合意をした者は、次に掲げる場合には、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
民法第五百四十八条の二(定型約款の合意)
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
作成方法
利用規約の作成方法としては、①他社サイトの利用規約を参考に作成すること、②作成代行会社等の第三者に作成依頼することの2つが考えられます。以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
①他社サイトの利用規約を参考に作成
利用規約の作成にあたっては他社の利用規約を参考にすることが有効な場合もあります。現に、インターネット上には著作権フリー素材として利用規約やその雛型がアップロードされています。
しかし、この場合に注意すべきなのは、こうしたものをそのままコピーして利用してはいけないということです。自身と同じサービスを提供している同業者であっても、事業内容が全く同じということはないはずです。自身の事業に沿ってオリジナルの利用規約を作成することを念頭に置き、他社の利用規約等は「参考にする」程度に利用するのが好ましいでしょう。
②作成代行会社に作成依頼
ECサイトの利用規約は作成代行会社に依頼することで自身が作成する手間を省くこともできます。代行会社によってはサイトの立ち上げ、運営に必要な法的書類を一括して作成してくれる場合もあります。
しかしながら、この作成代行の費用相場は20〜30万円であり、金銭的な負担がかかることや、ECサイトで展開するサービスが高度に専門的な場合、適切な利用規約が作成できない可能性もあり、作成を丸投げするのは好ましくありません。
理想的な作成方法・手順
以上から、利用規約の作成手順は
- インターネット等を活用し、まずは自身で情報収集をする
- 展開するサービスの分野に精通した弁護士等の専門家にリーガルチェックを依頼する
といった流れで行うことが理想的でしょう。
特に、コストダウンのために専門家によるリーガルチェックを省略することは、長期的にみると将来のトラブルを引き起こす原因となりかねず、②の手順は軽視すべきではありません。

特定商取引法について
次に、「特定商取引法に基づく表記」と、その前提となる、特定商取引法について解説します。
特定商取引法とは?
オンラインサービスとの関係では通信販売に関する規制が問題となりますが、特に、通信販売では、消費者が商品やサービスの情報を得る手段が広告に限られることや相互にコミュニケーションを取りづらく法律関係が不明瞭になる可能性が高くなります。こうした消費者トラブルの対策のために特定商取引法が制定されました。
「特定商取引法に基づく表記」とは?
特定商取引法では、消費者に誤解を与える様な表記や広告を規制し、トラブルの発生を防ぐ観点から通信販売において商品やサービスの広告をする際に、以下の事項を表示しなければならないことを事業者に義務付けています(特定商取引法11条)。
- 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
- 代金(対価)の支払時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
- 契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
- 事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号
- 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容及びその額
- 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
- 契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件又は提供条件
- 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
- 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
- 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
より詳細な情報は消費者庁が運営する「特定商取引法ガイド」にまとめられていますので、こちらも確認しておくことをおすすめします。
まとめ
今回は、ECサイトの立ち上げ・運営に際して最低限必要な法律のみを取り上げて紹介・解説してきました。冒頭にも挙げたとおり、ECサイトに関係する法令の数は膨大な上、社会情勢の変化等によって法令が改正されることもあります。
これらを網羅するのは、多大な時間と労力がかかります。不明点がある場合には専門家に相談することで未然にトラブルを防いだり、既存のトラブルを解決する一助になるかもしれません。

プロスパイア法律事務所
代表弁護士 光股知裕
損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。